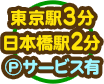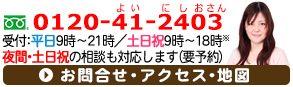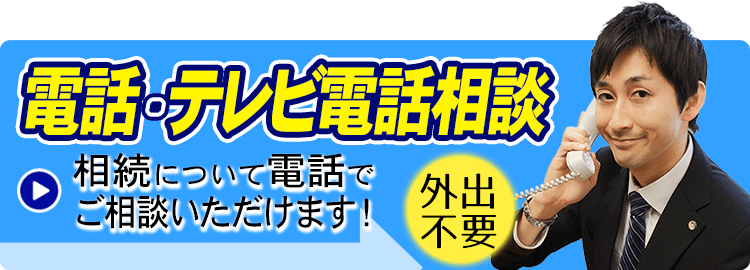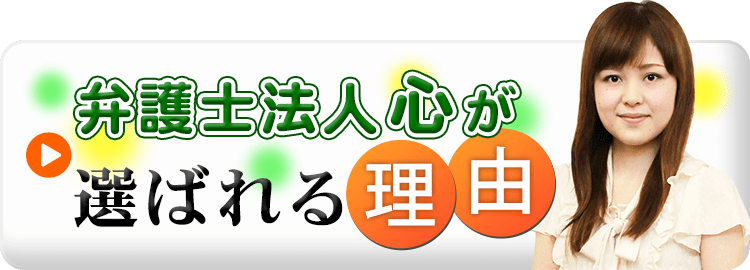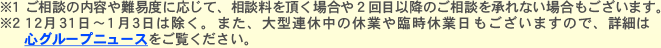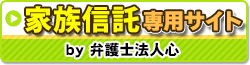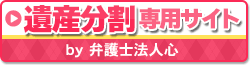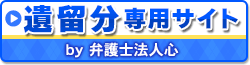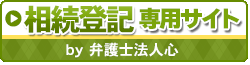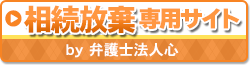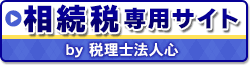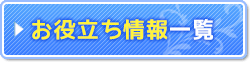相続財産の調査方法に関するQ&A
いつから相続財産の調査を始めるといいですか?
親族が亡くなった際は、悲しみの気持ちがある上に、葬儀など様々な手続きが必要なため、時間があまりないかもしれませんが、早めに財産の調査も行っていただきたいと思います。
相続が始まった場合には、債務も含めて相続財産を受け継ぐのか(単純承認)、プラスの財産の範囲内で負債も受け継ぐのか(限定承認)、自分の相続人としての権利を一切放棄するのか(相続放棄)の判断をする必要があります。
この判断をするためには、亡くなった方の財産状況の確認が重要となってくるためです。
預貯金を調査するためには、まず何をすればいいですか?
亡くなった方から生前に、使っていた口座を聞いていたような場合には、その口座がある金融機関に対して、残高の照会をすることが考えられます。
亡くなった方が生前にどの金融機関に口座を持っていたか分からない場合には、亡くなった方が持っていた通帳が残っていないか探して、照会をする金融機関を把握していく必要があります。
通帳も見つからず、亡くなった方がどの金融機関を使っていたか見当がつかないという場合には、亡くなった方の最後の住所地はどこか、その地域でよく利用されている金融機関はどこかといったことを考慮しながら、口座がある可能性の高い金融機関に照会をかけていくことになります。
このような場合、すぐに調査をすることが難しくなってくる可能性があるため、弁護士に財産調査を依頼することをおすすめします。
不動産を調査するためには、まず何をすればいいですか?
最終的には、不動産の地番や家屋番号を特定し、不動産の登記簿謄本を取得することになります。
そこで、地番や家屋番号を知るために、亡くなった方宛に届いた固定資産税の納税通知書を探すことで、亡くなった方がどのような不動産を保有していたかをある程度把握することができます。
しかし、これで把握ができるのは、固定資産税が課税される不動産だけです。
固定資産税の納税通知書だけでは、固定資産税が課税されない不動産があった場合、これを見逃してしまうおそれがあります。
そこで、市区町村役場等で、名寄帳を取得することも、相続財産の調査では有用です。
ただし、名寄帳は市区町村の単位で作成されるため、どのあたりに不動産があるかを把握した上で、地区ごとに取り寄せる必要があります。
株式等の有価証券を調査するためには、まず何をすればいいですか?
有価証券についても、まずは証券会社からの通知が亡くなった方の自宅に届いていないかを確認し、生前にどの証券会社と取引をしていたのかを知る必要があります。
預貯金の通帳がすでに見つかっている場合には、通帳の記載から証券会社が分かることもあります。
亡くなった方が利用していた証券会社を特定できたら、その証券会社に取引内容を開示するよう請求していくことになります。
相続財産調査は自分でもできますか? 相続手続には期限がありますか?弁護士にはいつ相談するべきですか?